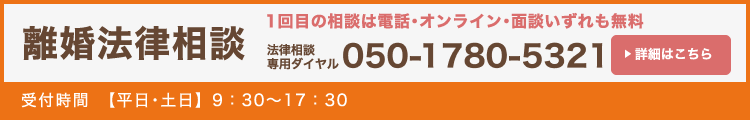離婚ブログ
過去の記事
- 11月
- 26
- Fri
弁護士の石井健一郎です。
離婚に伴う税金関係について,第1回は,財産分与と税金について,前回は,慰謝料と税金についてご説明しました。
【第1回コラム】財産分与と税金について
【第2回コラム】慰謝料と税金について
コラム第3回では,養育費と税金についてご説明します。
相続税法は贈与税の課税価格に算入しないものとして,『扶養義務者相互間において生活費又は教育費に充てるためにした贈与により取得した財産のうち通常必要と認められるもの』(同法21条の3第1項2号)を挙げています。
また,所得税法も『学資に充てるため給付される金品(給与その他対価の性質を有するものを除く)及び扶養義務者相互間において扶養義務を履行するため給付される金品』(同法9条1項15号)については課税しない旨を定めています。
したがって,基本的に贈与税・所得税のいずれにおいても課税の対象とはなりません(もっとも,「通常必要と認められるもの」との留保も付されていますが,それが養育費に仮託された所得隠しと疑われない限りは問題ないと思われます)。
今回は,離婚に伴う税金の問題のごく一部について,コラムを3回に分けて触れさせて頂きましたが,現預金や不動産に加えて有価証券(近年であれば特に仮想通貨)が含まれている場合には,別途対応が必要になり得ますし,また,離婚の成立の時期によって特例の適用を受けられないこともあり得ます。
弊所では所内で弁護士,司法書士,税理士が提携しており,離婚に伴う課税の問題についても見落とし無く対処することが可能です。
離婚の要否でお悩みの方のみならず,離婚に伴うお金の問題でお悩みの方も弊所までご連絡いただければと思います。
岐阜大垣事務所弁護士 石井 健一郎
- 11月
- 16
- Tue
弁護士法人愛知総合法律事務所の離婚コラムをご覧の皆様,弁護士の石井健一郎です。
前回は,離婚に伴う税金関係の財産分与についてご案内しました。
コラム第2回では,慰謝料と税金についてご説明します。
1 受け取る側の税金
離婚に伴って授受される慰謝料については,所得税法上「心身に加えられた損害につき支払いを受ける慰謝料その他の損害賠償金」(同法9条1項16号、同法施行令30条1号)として,非課税となっています。また,慰謝料自体が不法行為を原因として支払われるものであって贈与にはあたらない以上,贈与税も発生しません。
もっとも,財産分与の場合と同様,過大な支払いであったり,慰謝料の支払いに仮託した所得隠しと認定される場合には,贈与税が課される可能性があります。
2 渡す側の税金
財産分与と同様,現預金で渡した場合は非課税であるものの不動産の形で譲渡した場合には所得税が課税される可能性があります。
コラムの第3回では,養育費と税金についてご説明します。
岐阜大垣事務所弁護士 石井 健一郎
- 9月
- 30
- Thu
弁護士法人愛知総合法律事務所の離婚コラムをご覧の皆様,弁護士の中内良枝です。
今回は,財産分与についてのコラム第3回となります。
コラムの第3回では,生命保険が財産分与の対象となるかについて説明します。
コラムの第1回でご説明したように,財産分与は婚姻期間中に夫婦で形成した共有財産を分けるという制度です。そのため,共有財産から生命保険の掛け金を支払っていた場合は,その解約返戻金相当額は,預貯金と同様に財産分与の対象となります。
解約返戻金といっても,実際に生命保険を解約しなければならないわけではなく,基準日に解約したと仮定した場合の解約返戻金を対象とすることもできます。
もっとも,婚姻前に生命保険契約を締結し,保険料の支払いをしていたという方もいらっしゃると思います。このように婚姻前の財産(特有財産)による保険料の支払いがある場合には,基準時における解約返戻金の額をそのまま財産分与の対象とすることは適切ではありません。
このような場合には,解約返戻金のうち,婚姻期間の保険料の支払いに相当する金額を算出する必要があります。
具体的には,①別居時の解約返戻金から婚姻時の解約返戻金を控除する,②契約期間のうち婚姻期間で案分する方法などが考えられます。
生命保険については不動産や預貯金と異なり忘れがちであるため、ご注意していただければと思います。
- 9月
- 7
- Tue
一般論として、配偶者が不貞行為を行った場合、その不貞の相手方に対して慰謝料請求をすることができます。
では、既に長期間にわたって別居をしており、連絡も取っていない等、夫婦としての実態がないような状況で不貞行為があった場合でも、不貞相手は、慰謝料の支払い義務を負うことになるでしょうか。
これについては、判例上、
「婚姻関係がその当時既に破綻していたときは、特段の事情がない限り、不法行為責任を負わないものと解するのが相当である」
として、婚姻関係が破綻をした後に不貞行為があった場合は、慰謝料請求はできないとされています。
実務上も、不貞慰謝料請求に対して、婚姻関係が破綻している旨の主張がなされることがしばしば見られます。
しかしながら、上記の例のように、明らかに夫婦としての実態がないような場合はともかくも、単に夫婦仲が悪かったという程度の事情では、婚姻関係が破綻していると認められることは多くはありません(慰謝料金額を決定する上では、重要な要素にはなります。)。
何をもって「破綻」というかは非常に難しい問題ですが、不貞行為がされた時期の夫婦の状況について、個別具体的に判断をする他ないように思います。
当事務所では、不貞行為による慰謝料請求に関する事案も、数多く扱っております。
お困り事がございましたら、愛知総合法律事務所まで、ご相談を頂ければと思います。
- 8月
- 10
- Tue
愛知総合法律事務所のHPをご覧いただき,ありがとうございます。
東京自由が丘事務所の弁護士田村祐希子です。
さて,養育費の金額を算定する場合,養育費算定表が用いられることをご存じの方は多いかと思います。養育費算定表で導かれる金額は,離婚調停においても認定される可能性が高く,非常に有用ですが,皆さま,養育費算定表を正しく読み取れていますでしょうか。
本日は,特に誤りやすい自営業者の養育費の算出方法についてお話したいと思います。
給与所得者の場合には,養育費算定表の「給与」の目盛にあてはめる収入金額は,源泉徴収票の総収入金額,つまり,いわゆる手取金額ではなく,額面額になります。
自営業者の場合には,源泉徴収票がありませんので,確定申告書の「所得」金額を参照して導くことになりますが,「所得」金額をそのまま養育費算定表の「自営」の目盛にあてはめるわけではありません。
確定申告書における「所得」金額は,売上金額から諸経費を控除した金額です。諸経費には,減価償却費や特別控除額等の,実際に支出していない費目(以下「擬制経費」といいます。)が含まれています。このような費目は,あくまで会計上の擬制で計上される経費ですので,養育費の算定では控除する必要がありません。
そのため,確定申告書における「所得」金額に擬制経費を加算した金額が,自営業者の収入金額として養育費算定表の「自営」の目盛に当てはめるべき金額となります。
養育費は長期間に渡る支払要するものです。月額の多少の差額も,支払終期まで通算すると高額になり得ます。
一度決定した養育費を後で覆すことには困難を伴います。養育費の金額についてお悩みの方は是非お気軽に弁護士にご相談ください。
東京自由が丘事務所弁護士 田村 祐希子