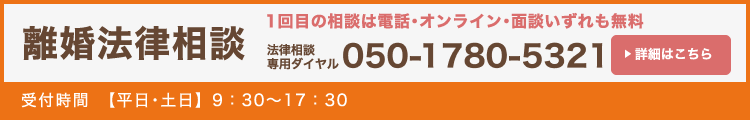離婚ブログ
過去の記事
- 3月
- 12
- Fri
愛知総合法律事務所のホームページをご覧の皆様,静岡事務所の弁護士の牧村拓樹です。
ありがたいことに多数の相談・依頼を受けており,離婚事件についても,多数の相談・依頼を受けております。離婚事件について,よく相談されることとして,離婚後の氏について相談されることがあります。今回は,離婚後の氏について,コラムを書きたいと思います。
婚姻によって氏を改めた配偶者は,離婚によって法律上当然に婚姻前の氏に復することになります。つまり,離婚することで,旧姓に戻ることになります。
一方で,離婚の日から3か月以内に,離婚の際に称していた氏を称する届をした場合は,離婚の際に称していた氏を使用することができます。これを婚氏続称といいます。
本来,氏の変更は家庭裁判所の許可が必要なのですが,婚氏続称の場合は,家庭裁判所の許可を要せずに変更が認められます。
では,離婚の日から3か月経過してしまった場合は,どうすればいいでしょうか。それは,氏の変更の基本に戻って,家庭裁判所の許可を得たうえで,氏の変更の届出をしなければならなくなります。
氏の変更の許可のためには,「やむを得ない事由」が必要なので,氏の変更を考えている方は,離婚の日から3か月以内に,婚氏続称届をするかどうか決定するのがよいかと思います。
離婚後の子の氏について
子の氏は,両親が離婚しても,当然変更されるわけではありません。
子が親と氏を異にしている場合には,子は,その親の戸籍に入ることはできません。
そうであるので,親が離婚の際に子の親権者になっても,子に自分と同じ氏を称させないと,子を自分の戸籍に入れることはできません。なお,大変わかりにくいですが,婚姻中の氏と婚氏続称の手続きをとった氏は,法律上別の氏とされますので,呼び方が同じでも,親と子の氏は異なるということになります。
そこで,氏を変更した親が子を自分の戸籍に入れるためには,「子の氏の変更許可」の申立てをする必要があります。
子の氏の変更許可の申立てについて,申立書類を揃えて申し立てをして,問題がなければ,許可がなされます。
家庭裁判所の許可によってすぐに氏が変わるのではなく,入籍届をしなければ,子の氏はかわりません。許可を得たら,入籍届も忘れずに行うようにしてください。
離婚後の氏を含む,離婚の問題について,悩みを持っている方は,愛知総合法律事務所に気軽にご相談いただければと思います。
- 3月
- 9
- Tue
ご相談の中でやはり多いのが,夫婦の一方による不貞行為を内容とするものです。
相談にいらっしゃる人の中には
不貞行為があったことは証拠があるので問題ない
と事前にお伝えいただける方も多いです。
不貞行為があったかどうかの証拠が大事
ということは,一般にも浸透しているのかなとも思います。
以上のように,皆様の関心の高い事情の一つである不貞行為ですが,
この不貞行為という言葉の定義は実は難しいものでもあります。
いわゆる肉体関係がこれに該当することはほぼ間違いありません。
しかし,肉体関係以外にも不貞行為と評価される行為も存在します。
実際に肉体関係がなくとも,夫婦間の婚姻関係を破綻に至らせるほどの異性間の交流について,不貞行為であると認められた裁判例もあります。
以上のとおり,どの場合に不貞行為に該当するかは,難しい問題もあるので,お悩みの方は一度ご相談されることをおすすめします。
ーー
愛知総合法律事務所岡崎事務所は,東岡崎駅南口徒歩1分の場所に位置しております。
初回法律相談は無料で実施しております。
不貞行為の問題でお悩みの方は一度弁護士にご相談されることをおすすめいたします。
岡崎市,幸田町,西尾市,安城市,碧南市,刈谷市,知立市,高浜市,豊田市を含む西三河地方の皆様からのお問い合わせをお待ちしております。
岡崎事務所のサイトはこちら
- 3月
- 8
- Mon
愛知総合法律事務所のホームページをご覧の皆様,春日井事務所の弁護士の池戸友有子です。
前回は離婚公正証書についてのコラムをお届けしました。
今回はお話し合いが難しく,調停に進む場合についてのアドバイスをさせていただきます。
離婚調停に進まれる方の多くは別居をされているかと思います。
もちろん離婚調停は同居していても申し立てることができますが,同じ自宅に家庭裁判所からのお手紙が届くなど少し違和感が生じるかもしれません。
それでは別居してから離婚調停を起こす場合はどのようなことに気を付けたらよいでしょうか。
別居前の財産関係資料の保全
離婚調停や,婚姻費用分担調停(別居中の生活費)では,ご夫婦の財産関係資料が必要になります。双方が包み隠さず開示をすれば何ら問題は生じませんが,必ずしもそうとは限りません。
そこで,別居前に機会があれば,以下のような資料のコピーを取っておくとよいでしょう。
①収入資料(源泉徴収票,所得証明書,給与明細など)
婚姻費用や養育費を決める重要な資料です。
②通帳
財産分与において重要な資料です。少なくとも表紙と直近の残高はコピーが取れるとよいでしょう。
③自動車関連
自動車も財産分与の対象です。車検証のコピーのほか,ローンがある場合,直近の残額がわかる資料があるとよいでしょう。
④不動産関連資料
固定資産税評価証明書やローンの支払予定表などのコピーがあるとよいでしょう。
⑤保険関連
別居時点での解約返戻金相当は財産分与の対象です。保険証書のコピーを取り,保険会社,証券番号だけはわかるようにしておきましょう。
婚姻費用分担調停の申立て
別居後に忘れてはならないのが婚姻費用分担調停です。 婚姻費用(別居後の生活費)は,家庭裁判所に申し立てた月から支払義務が生じることになります。 そのため,離婚調停に先立ってでも婚姻費用分担調停を申し立てることが重要です。
離婚調停の申立て
婚姻費用分担調停を申し立てたら,離婚調停を申し立てましょう。
婚姻費用分担調停と同時に申し立てることができなくても,第1回目の調停期日前に申し立てることができれば,同じ調停期日に調停を進めることができます。
以上が離婚調停までに欠かせないことの概要です。離婚案件は早め早めにご相談いただくことが後々大きな意味を持つことも多々ありますので,離婚が頭をよぎった際は,ぜひお気軽に弁護士にご相談ください。
離婚に関する相談は初回無料(面談相談は1時間無料)です。詳しくはこちら
- 3月
- 4
- Thu
離婚が成立した場合,ただちに相手方との関係が切れるかとそうはいかず,諸々の手続が必要となります。
そのひとつとして,公的な医療保険の問題があります。
離婚をしたのち,一方配偶者は,新たに自身で国民健康保険などの公的医療保険に加入する手続を行います。
この場合には,相手方配偶者に資格喪失届という書類を勤務先から取り付けてもらう必要があります。
このときに相手方が非協力な場合にトラブルになることがあります。
そして,その結果,無保険のために自由診療として支払わないといけなくなったとして,新たな紛争が起きることも考えられます。
相手方がそれでも非協力的な場合には,,いきなり相手方の勤務先等に苦情などの連絡を入れるのではなく,一度加入する保険の窓口に相談を必ずしてみるべきでしょう。
弁護士としては,このような無用な紛争は防ぎたいので,離婚成立後もこのような書類のやりとりまでは窓口として関与することが多いです。
ーー
愛知総合法律事務所岡崎事務所は,東岡崎駅南口徒歩1分の場所に位置しております。
初回法律相談は無料で実施しております。
離婚の問題でお悩みの方は一度弁護士にご相談されることをおすすめいたします。
岡崎市,幸田町,西尾市,安城市,碧南市,刈谷市,知立市,高浜市,豊田市を含む西三河地方の皆様からのお問い合わせをお待ちしております。
岡崎事務所のサイトはこちら
- 3月
- 1
- Mon
離婚分野についてのコラムをお届けしております。
今回は協議離婚をする際に必要不可欠ともいえる離婚公正証書についてどのように作成すればいいかをお話いたします。
離婚公正証書の作成
離婚公正証書の作成に当たっては,まずご夫婦で離婚条件を決める必要があります。離婚条件の中でも特に重要なのが,以下の内容です。
・養育費(お子様一人当たりの金額,支払いの終期など)
・お金の財産分与(支払期限など)
・不動産の財産分与(ローン負担者,名義変更時期など)
養育費や財産分与が発生しない場合は,離婚公正証書を作成せず,離婚届の提出のみでもよいかもしれません。
もっとも,この場合でも年金分割を希望する場合は,別途検討が必要です。
一方で,養育費や財産分与が発生する場合には離婚公正証書の作成は必要不可欠といえるでしょう。
離婚公正証書作成の大まかな流れとしては,以下のとおりです。
①双方で離婚条件を確定
②公証役場に電話をして公証人と面談の予約
③公証人と公正証書の文案を確定させ,公証人から指示された必要な資料を揃えて提出
④公正証書作成日に双方が公証役場に赴き公正証書が完成
公証役場は平日のみの対応で,何度もご夫婦で足を運ぶ負担は大きいです。
また,公証人がご夫婦の間をとりもって交渉・調整をしてくれるわけではありませんので,ご夫婦で条件面を確定して作成に臨む必要があります。
離婚公正証書の作成を弁護士にご依頼いただければ,ご夫婦のご意見を整理して過不足ない公正証書の文案を作成することはもちろん,公証役場との折衝やご依頼者様の代理人として公証役場での作成手続まで全てを弁護士が行うことができます。
せっかく公正証書を作成したのに後で後悔することがないように,ぜひ一度弁護士にご相談ください。
離婚に関する相談は初回無料(面談相談は1時間無料)です。詳しくはこちら
春日井事務所弁護士 池戸 友有子