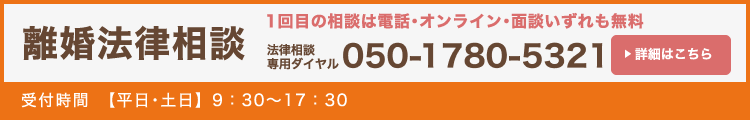離婚ブログ
過去の記事
- 2月
- 14
- Sun
岡崎事務所が開所してからあった大きな出来事としては,裁判所による養育費算定表の改訂があげられます。
具体的な内容については,裁判所のHPにアップされていますので細かくは一度ご覧いただくといいかもしれません。
さて,この養育費算定表の改訂の中でよくある質問として
過去に養育費の金額を決めたが,算定表が改訂されたので増額したい
とのご相談をされる方がいらっしゃいます。
これについて,まず当事者の合意が優先することは言うまでもありません。
では,算定表改訂が増額事由になるかというと,
今回の「養育費,婚姻費用の算定に関する実証的研究」の中に,「本研究の発表は,養育費の額を変更すべき事情変更に
は該当しない」との記載がされています。
したがって,今回の算定表の改訂の事実だけではこれまで養育費の受け取っていた方にとっても,養育費の金額が変わる事情としては利用できないということです。
違う観点でみれば,これを理由として養育費の増額を認めるとすれば,裁判所は養育費の増額調停の申立てが急増してしまい,処理できないことからも無理のない見解なのかと思います。
既に,養育費の金額の合意をした当事者の方たちについては以上のとおりですが,これから養育費の額を決める人たちからすれば,みなさん関係のある内容だと思います。
養育費のことでお悩みの方は,一度弊所にご相談いただけると幸いです。
ーー
愛知総合法律事務所岡崎事務所は,東岡崎駅南口徒歩1分の場所に位置しております。
初回法律相談は無料で実施しております。養育費を含む離婚問題でお悩みの方は一度弁護士にご相談されることをおすすめいたします。
岡崎市,幸田町,西尾市,安城市,碧南市,刈谷市,知立市,高浜市,豊田市を含む西三河地方の皆様からのお問い合わせをお待ちしております。
- 1月
- 29
- Fri
浮気をされた,暴力を受けた,モラハラを受けた…といった事情で離婚を決意した場合に,慰謝料の請求が可能であることは,多くの方がご存じのことだと思います。
そこで,一歩進めて,慰謝料の請求方法について若干の説明をさせていただきたいと思います。
⑴ まず,離婚協議において慰謝料の主張をする場合が考えられますが,このパターンはあくまでも当事者の話合いの次元の話なので割愛します。
⑵ 次に,離婚調停の申立てと同時に主張する場合が考えられます。これは,離婚調停内で,親権の所在や財産分与,養育費等を決めていく中で慰謝料についても取り決めてしまおう,ということです。
もっとも,調停で合意ができない場合に,まず先に離婚の成否だけ調停で決めてしまった後に財産分与や養育費については裁判所に審判で決めてもらうことは可能ですが,慰謝料の審判を求めることはできないことになっています。
したがって,パートナーが不貞や暴行の事実を頑として認めない場合には調停では解決し得ないことになります。(肌感覚で申し上げれば,よほど決定的な証拠を突き付けない限り,パートナーは不貞や暴行の事実を否定してくるので,慰謝料については話がまとまらないことが多いように思われます。)
なかには,財産分与の審判において慰謝料の要素も加味してくれたというケースもありますが,セオリーになっているとまでは言えず,かかる考慮をしてくれるか否かは裁判官の好みによっても分かれ得るところですから,過度の期待は禁物でしょう。
⑶ そして,離婚訴訟を提起した際に主張することが考えられます。
この際,離婚訴訟を提起する中で慰謝料の支払いを求めることもできますし,離婚訴訟を提起した後に慰謝料の支払いを求めて損害賠償を追加して請求することもできます(別々に提起をした後,相当と認められる場合には,家庭裁判所に併合することも可能です)。
ここまでくれば,主張と立証を尽くして不貞や暴行,モラハラの事実を裁判官に認めさせることさえ出来れば慰謝料の請求が認められることになります。
以上が慰謝料請求に関しての簡単なイメージとなりますが,いかがでしたでしょうか。もし,現在もしくは近い将来において,離婚に伴う慰謝料の請求を行うことを検討されているのであれば,一度事務所までご相談ください。
岐阜大垣事務所 弁護士石井健一郎
岐阜大垣事務所弁護士 石井 健一郎
- 12月
- 8
- Tue
離婚をするにあたってまずは別居を始める,もしくはすでに別居状態にある夫婦は多いと思います。この場合に,配偶者と比較して自分の方が収入が少ない場合は,相手に対し婚姻費用を請求することが考えられます。
夫婦には,それぞれの資産や収入等を考慮して,婚姻から生じる費用を分担する義務があり,別居等によってその義務が果たされていない場合は,婚姻費用を金銭で請求することができるようになります。
では,この婚姻費用はいつの分から相手に支払を求めることができるのでしょうか。
これについては,扶養が必要な状態が発生した時点とするもの,扶養が必要な状態を知ることができた時点とするもの,別居時点とするもの等,様々な考え方がありますが,実務上は,支払を求める側が相手方に対し,婚姻費用の請求をした時点と考えられることが多いです。
そのため,婚姻費用の支払いを相手に求めたい場合は,できる限り早く相手に請求をするべきということになります。
ただ,「請求」といっても,どのようなことをすればよいのでしょうか。
これについては,考え方は大きく2つあります。一つは内容証明郵便等を送っておけばよいという考え方,もう一つは婚姻費用分担調停を申し立てておく必要があるという考え方です。
従前は,婚姻費用の分担の調停を家庭裁判所に申し立てる必要があるという考え方が多数でしたが,最近は専ら,内容証明郵便等を送っておけば,内容証明郵便等が相手方に到達した時点で「請求」があったと認める考え方が支配的です。
そのため,相手方に対し婚姻費用の支払いを求めたい場合は,取り急ぎ,その旨記載した内容証明郵便を送っておけば,仮にその後調停や裁判などで争いになったとしても,少なくともその到着時点以降からは婚姻費用の支払いを受けることが期待できます。
請求する以前の過去の婚姻費用についても,離婚するにあたっての財産分与の中で考慮することができるという考え方もありますが,後々争いになったときに確実に婚姻費用を受け取るには,やはり内容証明郵便等を送っておくのが適切かと思います。
ただ,内容証明郵便等の記載内容ひとつとっても,どのように記載すればいいのかわからないといった悩みもおありだと思います。ぜひ一度弊所の弁護士にご相談いただければと思います。
名古屋丸の内本部事務所 弁護士中村展
浜松事務所弁護士 中村 展
- 11月
- 12
- Thu
離婚事件において,財産分与は特に争われやすい争点の一つといえます。
夫婦が離婚する場合,財産分与が問題となることはご存知の方も多いと思いますが,そもそも財産分与の「財産」とはいったい何を指すのでしょうか。
別居して共有財産の使い込みが起きた場合
例えば,ある夫婦が離婚協議中で別居していたとします。
別居時,夫婦の共有財産として預貯金が500万円ありましたが,別居して半年後,夫婦の一方がこれを使い込み,0円となってしまいました。
この場合,夫婦の財産はもう残っていないから,分ける財産もない,ということになってしまうと困りますよね。
共同生活をしている夫婦が婚姻中に築いた財産は,夫婦が協力して形成したものであるから、離婚時にはこれを共有財産として夫婦で分けるべきだというのが,財産分与の基本的な考え方です。
この考え方に基づけば,財産分与の「財産」とは,夫婦が共同生活により協力して築いた財産に限られるということになります。
夫婦が別居した場合,その時点で夫婦の協力関係はなくなったと考えられますので,別居後の財産が増えても減っても,それは考慮しないとするのが原則的な考え方となります。
上のケースだと,夫婦で協力して形成した財産が別居時に500万円あったのですから,たとえ今は0円になっていても,500万円が財産分与の対象となり,この半分の250万円を夫婦の一方が他方に請求するということになります。
ただ、そうであるからといって安心できるものでもなく,この預貯金以外に財産がないようなケースなどでは,預貯金を使い込んだ相手方から250万円を回収するのが困難なこともしばしばあります。
離婚でお悩みの方は,お早めに弁護士に相談されることをおすすめします。
名古屋丸の内本部事務所 弁護士西村綾菜
■財産分与に関するトラブル解決事例
・相手方に財産を浪費されて離婚訴訟にて離婚が成立した事例はこちら
離婚のご相談は弁護士法人愛知総合法律事務所までお気軽にお問合せください。
- 10月
- 15
- Thu
結婚する年齢が高くなったこともあり、結婚前に財産を形成していたという事案も少なくありません。
今回は、財産分与における独身時代の財産の取り扱いについてお話します。
離婚する際には、財産分与を行う必要があります。財産分与とは、夫婦が婚姻中に形成した財産を清算するものと説明されます。したがって、財産分与の対象となるのは、結婚した後に夫婦協力のもと得た財産ということです。独身時代に所有していた車や預貯金などの財産は、財産分与の対象外ということになります。
理論的には、結婚前に有していた財産は財産分与の対象外ということになりますが、その財産が結婚前に有していたものかどうか、判断できるか検討してみます。車であれば、購入した時期がわかれば、結婚前に取得したものか判断できます。
次に預貯金について、具体例で考えてみます。預金口座を1つしか持っていなくて、結婚前に200万円の貯金があったと想定します。結婚後、その口座には、毎月給料が入金されます。他方で、同じ口座から、毎月家賃や生活費が出金されます。10年の結婚生活の末、離婚しようと思った時には、貯金が500万円あったとします。
口座に残っている500万円は、結婚前に貯めていた200万円に、結婚後新たに貯めた300万円が加わったものであると断定できるでしょうか。
10年間出入金が繰り返された口座に、今ある貯金が、いつ入金されたお金が残っているものなのか特定することは、事実上不可能です。1つの口座に結婚前の貯金と結婚後の出入金が混在するような場合、結婚前に有していた預貯金と結婚後に取得した預貯金を区別することができないため、財産分与の対象から結婚前に有していた預貯金を除外することは難しいです。
他方、これが定期預金で、結婚前にあった定期預金が結婚後も手付かずのまま更新し続けられていたときは、当該定期預金は、結婚前に有していた財産であると特定できます。この場合は、財産分与の対象から除外できます。
なお、少し補足すると、結婚前に有していた預貯金も含めて、全額が財産分与の対象になった場合でも、公平の見地から、財産分与の割合が修正されることはあります。 今回は、独身時代の財産が財産分与の対象となるかという話を書きましたが、相続で取得した財産や家族の援助で取得した財産など、財産分与から除外されうる財産はあります。
どの財産が財産分与の対象になるか、何も知らないまま話をすることで、渡し過ぎているのではないか、あるいは、受け取れるものを受け取れていないのではないかと気になった際には、弁護士にご相談いただければと思います。