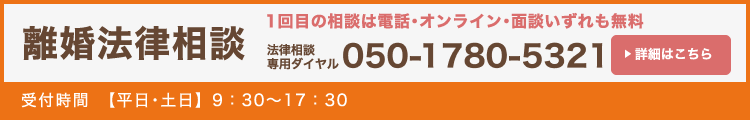離婚ブログ
過去の記事
- 4月
- 10
- Fri
婚姻費用・養育費については、いわゆる標準算定表を用いて、およその目安の金額を出します。
標準算定表を用いるうえで、義務者(婚姻費用・養育費を支払う側)と権利者(婚姻費用・養育費を受け取る側)の収入を認定する必要があります。
義務者が無収入である場合(例えば、専業主婦(夫)であった場合、一時的に退職している場合など)は、収入は0円として算定することになるのかという点につき、よく相談を受けます。一般的には、就労できない客観的・合理的事情がなく、単に働きたくないなどの事情により収入が無い場合には、義務者が働いた場合にはどの程度の収入を得るであろうかを推測して収入を認定することとなります。この推測が難しい場合に、賃金センサス(厚生労働省が統計を取っている労働者の賃金の平均のこと)を用いる場合があります。
また、専業主婦(夫)であった妻(夫)の別居後の収入を推測する場合にも、パートタイム労働者の賃金センサスなどを用いて収入を認定することもあります。婚姻費用・養育費の支払を求められている場合で、現時点では相手が無収入であっても相手に就労能力がある場合には、ご注意いただければと思います。
名古屋丸の内本部事務所弁護士 木村 環樹
- 3月
- 31
- Tue
婚姻費用や養育費の算定において,権利者・義務者双方の収入が考慮されていることは,よく知られているのではないかと思います。婚姻費用・養育費を算定する上で良く用いられている算定表でも,権利者,義務者の収入によって相関的に金額が決定される仕組みになっています。
単純化して言えば,権利者の収入が低く,義務者の収入が高額であるほど,婚姻費用・養育費の額は高額となり,権利者の収入が高く,義務者の収入が低額であるほど,婚姻費用・養育費の額は低額となります。
給料をもらっているサラリーマンであれば収入は前年の源泉徴収表を見れば明らかになりますし,個人事業主(自営業者)の場合,収入の認定は確定申告書の所得額によることになります。
これらの公的資料によって単純に収入を認定できればよいのですが,時として問題が生じることがあります。
例えば,確定申告書の所得額について,経費が過剰に計上され,見かけ上の所得が不当に抑えられている場合もあります。
この場合,確定申告書だけではなく,収支内訳書や青色申告決算書などを精査して,不自然な経費の計上がないかを検討しなければなりません。特に,離婚係争が長期に及び,養育費を請求する相手方が自営業者である場合,相手方が,養育費の額を低く抑えるために確定申告書の所得額を不当に抑えていないか,という視点で確認する必要があります。
また,給与所得者でも,実質的に個人事業と変わらない規模の会社の役員の場合,その給与額(役員報酬額)は恣意的に操作されている可能性があります。離婚紛争発生後に,それまでの役員報酬額と比較して極端に役員報酬が減額されている場合は,養育費を低く抑えるために操作されている可能性が疑われます。
婚姻費用や養育費の算定について,公的資料では収入が適正な収入が認定できない場合,厚生労働省の作成している統計資料「賃金構造基本統計調査」(賃金センサス)に基づいて認定される場合があります。例えば,平成30年の,男性,大学・大学院卒業,40歳~44歳の平均賃金は719万9200円とされており,このような統計上のデータに基づいて収入を認定し,婚姻費用や養育費が算定されることがあります。
- 1月
- 10
- Fri
令和元年12月23日に、最高裁判所より、養育費、婚姻費用の新しい算定表が発表されました。 当事務所の全相談室には、新算定表を完備しています。 今後は、新算定表に沿って、養育費、婚姻費用が決定されることとなります。 新算定表は、従来の旧算定表と基本的な枠組みは変わっていません。 旧算定表の提案から15年余りが経過していることから、社会実態を反映した内容となっています。 新算定表の基準によれば、養育費、婚姻費用の金額は概ね増加するケースが多くなっています。 また、旧算定表と比べてお子様が0歳から14歳の場合と、15歳以上の場合の金額の差は少なくなっています。 今回の新算定表の発表が、既に決定済みの養育費、婚姻費用の金額を変更すべき事情変更には該当しないとされていますので、今回の発表だけに基づいて、養育費、婚姻費用の増額を求めることは困難と思われます。 但し、他の事情変更がある場合に、新たに養育費、婚姻費用を算定するにあたっては、新算定表を用いることが期待されるとされています。 また、成年年齢引き下げにより、支払義務の終期が18歳に変更されるかという点については、改正法の成立又は施行前に「成年」に達する日まで等と定められた「成年」については基本的に20歳と解することが相当との考え方も示されています。 今後は,単に成年とするのではなく、満20歳、満18歳などと具体的に記載することが求められています。具体的な養育費、婚姻費用の金額等の内容については、弁護士にお尋ね下さい。当事務所としましては、このような改正について、迅速に対応をして参りたいと思います。 日進赤池事務所 弁護士水野憲幸
- 11月
- 18
- Mon
家事審判に対しては,特別の定めがある場合に限り即時抗告することができます。
婚姻費用(養育費)の審判が出されて,その金額に不服があるという場合には,高等裁判所に即時抗告(不服申立て)することができます(抗告状の提出先は,審判をした家庭裁判所に提出)。
ただし,即時抗告ができるのは,審判の告知を受ける者についてはその告知を受けた日から,2週間以内にしなければならない(家事事件手続法86条1項,2項)とされていますので,注意が必要です。
なお,家事事件手続法では,家事審判事件の抗告審に関する規律として,民事訴訟法304条等に定める不利益変更禁止の原則や,同法第293条に定める附帯抗告に関する規定が特におかれていません。
家事事件手続においては,裁判所は公益性を考慮し,後見的な立場から判断をするものであるという原則があり,抗告された以上は,高等裁判所は,有利不利にかかわらず,高等裁判所が正しいと考えた裁判ができるようにしています。
つまり,婚姻費用の月10万円を不服として抗告したら,先方が抗告していないにも関わらず,月5万円に減額されてしまう場合もあり得るとういことです。
一方で,抗告したら不利になるかもしれないと迷い抗告しなかった結果,先方のみが抗告した場合,こちらは附帯抗告はできません。
抗告するか否かは,見通しをふまえて,慎重に判断する必要があります。名古屋丸の内本部事務所 弁護士奥村典子
- 10月
- 31
- Thu
こんにちは,小牧事務所所長弁護士の遠藤悠介です。 今回は,遠距離別居の際の裁判手続きについてお話しさせていただきます。例えば,夫婦仲がうまくいかず,離婚に至る前に別居を選択された場合,当事者の一方が,実家がある地へ引っ越してしまうなど,遠距離の別居に至ってしまう場合は少なくありません。この場合,お互いの話し合いで解決ができないとなると,裁判所へ調停の申し立てをし,調停委員を通じて話し合いによる解決を目指すことになりますが,裁判所の管轄(どこの裁判所で調停を行うことができるか,ということです)は申立を受ける相手方の住所をもとに決定されます。 そのため,離婚の調停を行う場合には,期日があるたびに,相手方の住んでいる地域まで出向く必要があるのが原則です。 ただし,弁護士にご依頼いただく場合には,電話会議による方法により期日を開くことが可能になります。依頼者の方には法律事務所にお越しいただき,事務所の電話を通じて調停委員とお話しすることができるため,時間的,費用的に非常に経済的です。ただし,交渉事ですので,調停委員と顔を合わせて話をした方が順調に進む場合もございますので,ご依頼いただける場合には,具体的事案に沿って,電話会議を選択するか,例えば初回は電話会議ではなく実際に現地に行って調停を行うこととするなど,ご提案をさせていただければと存じます。 まずは,お気軽にご相談いただければ幸いです。小牧事務所 弁護士遠藤悠介