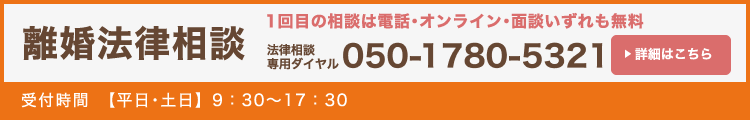離婚ブログ
過去の記事
- 10月
- 1
- Tue
こんにちは。高蔵寺事務所の弁護士の服部文哉です。
離婚のご相談のケースの一つとして,相手方から強く離婚を求められているけれど,こちらは離婚に応じるつもりがないというものがあります。このようなとき念のために注意しなければならないのが、相手方が離婚届を単独で作成、提出してしまわないか、ということです。
夫婦の一方が相手に何らの断りもなく離婚届を作成、提出してしまったとしても離婚は無効です。したがって上記のようなケースでは離婚の無効を主張することができます。
しかし,実際に離婚の無効を勝ち取るためには、協議離婚無効の調停を起こし、調停で決まらなければ協議離婚無効の訴えを起こし、勝訴する必要があります。また戸籍については別途訂正の申請をする必要があります。相手が勝手に離婚届を出してしまったというだけで、このような時間と労力のかかる手続きを強いられる危険性があるということになります。
こうした事態を防ぐためには、前もって役所に離婚届の不受理申出をしておくことが考えられます。この申出をしておけば、申し出をした本人の本人確認が取れない限り離婚届が受理されないため、上記のようなリスクを防ぐことができます。
不受理申出自体は役所に不受理申出書の書式が用意されているはずですので、運転免許証などの本人確認書類を持参して役所に行けばすぐに提出できるはずです。
上記のように、法律問題に発展する前に防止することがトラブルの早期解決の基本です。何かお困りごとがございましたら、是非早めに当事務所までご相談下さい。高蔵寺事務所 弁護士服部文哉
- 8月
- 30
- Fri
離婚が現実的になった場合,夫婦が別居することが良くあります。
離婚の希望がある場合,親権,養育費,慰謝料,財産分与等,離婚の条件を話し合うことになるのですが,離婚の条件とは別に,まず婚姻費用が問題となります。
婚姻費用という言葉は法律用語で聞き慣れないものかと思いますが,生活費のことと考えて頂いてかまいません。夫婦が別居したとしても互いに扶養する義務あることには変わりありませんので,夫婦の収入に差がある場合,原則として婚姻費用の支払義務が生じます。
以下,良くある疑問にお答えいたします。
Q 勝手に出ていった場合でも,婚姻費用を受け取ることはできるか?。
A 可能です。
Q 相手の不貞で別居に至ったのだから,お金を渡す必要ないのでは?
A 不貞等,相手に責任があることが明らかな別居の場合は,相手分の生活費を減額した裁判例があります。
Q 相手が婚姻費用を払いません。請求の手段は?
A 裁判所での調停を申し立てる必要があります。相手の収入が分からなくても,手続きのなかで明らかにしていくことになりますので,すぐに弁護士に相談することをお勧めします。
Q 婚姻費用は,過去に遡って請求できますか?
A 裁判所で過去分を認めて貰うのは難しいので,相手との交渉になります。原則として請求した月の分からしかもらえませんので,できるだけ早く弁護士に相談し,調停等で請求することをお勧めします。
Q 相手の携帯料金等を払っているのですが,婚姻費用の額を決めるにあたって考慮してもらえますか?
A 相手の生活費を払っている部分があるのなら,額を決めるにあたって考慮してもらえます。
Q 調停で決まった婚姻費用の支払が滞ったのですが?
A 給与等を強制執行することになります。ご相談下さい。
名古屋藤が丘事務所弁護士 長江 昂紀
- 6月
- 14
- Fri
こんにちは。津島事務所の加藤耕輔です。離婚のご相談の際,よく耳にする話として,「住宅ローンを養育費の代わりとして夫に支払ってもらう」という話があります。妻と子は,そのまま自宅に住み続け,夫の側で妻と子が住む自宅の住宅ローンを支払い続ける代わりに養育費はなしとする,というお話です。こうしたお話を聞いたとき,いつも,私は「お勧めしない」とお伝えしています。まず,住宅ローンを借りている金融機関等との関係で問題があります。金融機関は,住宅ローンの名義人である夫が自宅に住み続けることを前提として,住宅ローン審査を通しています。そのため,住宅ローン契約書に,住居移転等の場合に連絡・許可等を求めるという条項が入っている場合が多いかと思います。実際には,金融機関も,「返済してくれさえすれば・・」というスタンスで,あまり何も言ってこないことがそれなりに多い気はしますが,安易な判断は禁物です。また,離婚するとき,当事者は,数年先のことしか考えていないことが多いのですが(これ自体はしょうが無いかと思います),・住宅ローンを完済した場合,どうするのか。・夫が再婚して,再婚相手に相続権が発生した場合どうするのか。等,将来勃発しうる問題についても考える必要があります。いずれも離婚後,年月が経った後の話ですから,より関係も希薄になっており,新たな法的トラブルに発展するリスクは大きいかと思います。以上の理由から,私は,「養育費代わりに住宅ローン支払い」という形は「お勧めしない」とお伝えしています。もっとも,例えば,「お子さんが高校2年生であと2年間だけ環境を変えないようにしたい」といったケースのように,終期が確実な場合には,無償の使用貸借と養育費支払いという形や,場合によっては賃貸借契約を交わすことで,2年間だけ事実上「養育費の代わりに住宅ローン支払い」という形を取ることもありうるかと思います。実際に,過去に,数年間の賃貸借契約を交わして,お子さんが高校卒業するまで生活環境を変えないという形で調停合意した事案がありました。その際,賃貸借契約を交わすと借地借家法が適用されてしまい,夫側は不利な立場になりうるため,借地借家法の適用がない定期建物賃貸借(借地借家法38条第1項)であることを調停条項に盛り込んでもらったことがあります。 津島事務所 弁護士加藤耕輔
津島事務所弁護士 加藤 耕輔
- 6月
- 3
- Mon
こんにちは。名古屋丸の内本部事務所の弁護士中内良枝です。
私は普段,離婚の相談を多く受けているのですが,相談者の皆様からよく聞かれる質問の一つに,「離婚調停ってどういう手続ですか?」というものがあります。
私たち弁護士は,毎日のように裁判所へ行っているので慣れていますが,皆様にとっては一生に一度あるかないかの経験だと思います。いざ離婚をしようと決意をされても,今後どのように離婚の手続が進んでいくのか,不安になるお気持ちはよく分かります。
そこで,離婚手続の中でも,一般の方にはイメージが湧きにくい,裁判所を介した手続のうち,離婚調停について,具体的にどのように進んでいくのか,簡単にお話させていただきます。
なお,離婚手続の全体的な流れや解説については,こちらも併せてご参照ください。
まず,調停というのは,裁判所で行われる一種の「話合い」の手続です。この点で裁判所の判断が下される裁判(訴訟)とは,異なります。
裁判所の「裁判手続の案内」にも,「調停は,裁判のように勝ち負けを決めるのではなく,話合いによりお互いが合意することで紛争の解決を図る手続です。」と記載されています。
裁判所と聞くと,何か怖いイメージがあるかもしれませんが,これを聞いて少しハードルが下がったのではないでしょうか。
また,離婚のような家族間の問題については,一次的には当事者間で解決することが望ましいと考えられていることから,いきなり裁判をするのではなく,まずは調停を申し立てることになります。これを調停前置主義といいます。
調停を申し立てると,調停が開催される期日が決まります。そして,当日裁判所へ着くと,受付をして,待合室で呼ばれるのを待ちます。
調停室には,2名の調停委員(男女1名ずつ)がおり,当事者が交互にその部屋に入り,話をします。調停委員は,各当事者から事情や意見を聞いて他方当事者に伝えたり,助言やあっせんをしたりします。
1回の期日で話し合いがまとまらない場合には,次の期日を指定してもらいます。これを数回繰り返し当事者間に合意が整えば,合意した内容を記載した調停調書を作成し,終了となります。
合意した内容を記載した調停調書には,裁判の判決と同一の効力があります。そのため,合意するかどうかは,メリット・デメリットを比較の上,慎重に決める必要があります。また,調停委員はあくまで中立的な立場にあるので,一方当事者の利益だけを考えてくれるわけではありません。そのため,自分の主張を理解してもらえるよう,説得的に伝えることが重要になります。
調停はご本人でもできる手続ではありますが,調停委員にどのように話をしていいか分からない,どのような内容であれば合意をするべきか分からない,メリット・デメリットを踏まえ納得のいく離婚がしたいという方は,ぜひ一度,私たちにご相談いただければと思います。
名古屋丸の内本部事務所 弁護士中内良枝
- 4月
- 5
- Fri
財産分与請求権とは、離婚した者の一方が他方に対して財産の分与を求める権利のことをいいます(民法768条1項)。財産分与というと、多くの方は、婚姻期間中に蓄財された財産を2分の1にすること(いわゆる2分の1ルール)を思い浮かべることと思います。もちろん、上記が財産分与の大原則ではあるのですが、財産分与には、1 夫婦が婚姻中に協力して得た財産の精算(清算的財産分与)2 離婚後の経済的弱者に対する扶養(扶養的財産分与)3 相手方の行為により離婚をせざるを得なかったことについての慰謝料(慰謝料的財産分与)があると言われております。そのうち、扶養的財産分与が認められるためには、請求者に扶養の必要性があり、被請求者(請求される側)に扶養の能力があることが、必要になります。また、その金額は、婚姻期間、有責の有無及び程度、夫婦の収入、年齢、子の養育状況、病気や身体あるいは精神の障害の有無及び程度等、様々な事情を考慮して決定されます。上記のとおり、財産分与の中心は清算的財産分与にありますので、扶養的財産分与は、補充的・限定的に認められており、期間としても、一方の生計が安定するまでの一時的なものに留まることが多いです。以上のとおり、扶養的な財産分与については法律上難しいところもありますので、扶養的財産分与の請求を考えておられる方、また、請求を受けている方、ぜひ弁護士にご相談を頂ければと思います。 岐阜大垣事務所 弁護士佐藤康平