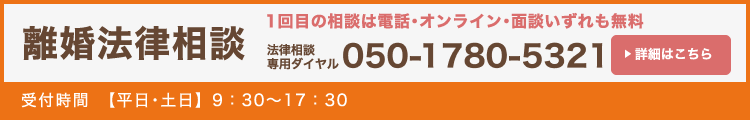離婚ブログ
過去の記事
- 8月
- 23
- Thu
配偶者の浮気が発覚した・・・ 配偶者が一切家事を手伝ってくれない・・・ 暴言がひどくて一緒に暮らすことが難しい・・・ 夫婦が離婚を決意する時期・理由については様々です。
しかし、離婚を決意したほぼ全ての夫婦が行うことになるのが、別居です。 一般的に、別居が一定期間続けば、離婚原因とされているように、夫婦が離婚に向かうにあたって、最初に行うべきことは別居を開始することとも言えます。
ただ、別居を開始することで、婚姻費用の分担、子の監護者の指定・子の引き渡し等、法的な問題が生じることも事実です。
ここで、弁護士の下にご相談にいらっしゃる相談者の方は、別居後にご相談に来られる方が多いです。しかし、できることであれば、別居を開始する前に一度相談にいらっしゃることをお勧めします。なぜかというと、別居を開始し、離婚に向けた協議の中で、財産分与に関し、相手方が財産を開示してくれればいいのですが、全ての財産の開示を行わないことがよく見受けられます。
この場合、自分たちで相手方の財産の存在を主張立証する必要があります。「財産がこんなに少ないわけがない!」と言うだけでは足りないのです。
また、配偶者がもし浮気の疑いがあるときや、口頭で浮気を認めている場合でも、後に主張をひるがえし、証拠がないことで不利になる可能性もあります。
このため、仮に別居を考えているときには、同じ空間にいること自体が嫌になることがあるかもしれませんが、すぐに別居するのではなく、週末だけでも一度自宅の中を探して、証拠になりそうなものはないか確認することで、きちんと証拠や資料を入手することができるかもしれません。
このような行動は、別居を開始した後では難しいものです。
ただし、家庭内で暴力がふるわれているようなケースであれば、お体の安全が第一ですので、直ちに別居を開始すべき場合もありますので、ご注意ください。 以上のように、別居を開始する前に、できる限り資料を収集すべきことをお勧めしてますが、「どのような証拠があれば不貞行為を証明できるのか。」「財産分与でこちらが有利になるような資料は何なのか。」については、なかなかご自身で判断することは難しいと思います。
このことからも、別居を開始する前に、弁護士に相談することで、どのような資料を集めるべきかアドバイスを受けることができます。
もし、離婚を考え、別居をしようとしている方がいらっしゃいましたら、一度ご相談していただければと思います。
弊所は、愛知県内には、名古屋丸の内、新瑞橋、藤が丘、小牧、津島、春日井、日進赤池、高蔵寺、岡崎の9箇所に、また岐阜県内には大垣に1箇所支店を設けていますので、なかなか名古屋の中心まで出てくることが難しい方でもご相談に来て頂くことが可能です。
また、事務所にお越しいただくことが難しい方であれば、電話でのご相談も可能ですので、一度弊所までお問い合わせください。
岡崎事務所 弁護士安井孝侑記
- 7月
- 20
- Fri
離婚の際に養育費額を定めたとしても,その後義務者による支払いが滞ってしまうことが多いのが現状です。そこで,今回は,養育費の支払確保の手段について,ブログを書きたいと思います。 1 当事者間で養育費額が合意した場合は,執行受諾文言付公正証書で合意しておくとよいです。そうすれば,養育費の支払が滞った際は,給料の差押えなどの強制執行手続をとることが可能だからです。
また,養育費について当事者間で取り決めができないときは,家事調停を利用することが考えられます。印紙代は1200円と比較的安価なため,気軽に利用することができます。それに,調停で養育費額について合意に達しない場合は,裁判所が審判手続で養育費額を決めてくれます(なお,離婚に伴う場合は人事訴訟で判断されることになります)。その結果,審判という強制執行可能な形で養育費額が決定されます。2 では,調停や審判などで養育費が定められた後に,義務者の支払いが滞った場合,どのように養育費の支払を確保して行けばよいのでしょうか。この点に関し,法は,以下の履行確保手段を用意しています。
(1) 1つは,履行勧告です。履行勧告とは,調停や審判で定められた義務の履行を怠る義務者に対し,家庭裁判所が,権利者の申立てにより,義務を履行するように勧告をする制度です。しかしながら,履行勧告に従わない場合の制裁は定められていないため,実効性には乏しいのが現状です。
(2) 1つは,履行命令です。履行命令とは,家庭裁判所が,権利者の申立てによって,義務者に対し,その義務の履行をなすべきことを命じる制度です。履行命令に従わない場合は10万円の過料に処される場合があります。
(3) 1つは,強制執行手続です。強制執行手続をとるためには,調停調書,審判,判決が必要になります。また執行受諾文言付公正証書を作成した場合も強制執行手続を利用できます。相手方が給与所得者である場合などは,給料や賞与(ボーナス)の差押えを裁判所に申し立てられますので,有効な手段です。
そして養育費の場合,不履行が一部でもあれば,将来の給料に対する差押えもできるようになり,また差押えの範囲も可処分所得の2分の1に広げられました。
もっとも,勤務先等は差し押さえる側で調べなければならないため,勤務先が分からない場合は,強制執行手続も暗礁に乗り上げてしまうことがあります。
(4) その他,間接強制の方法等が存在します。3 まとめ
養育費の支払を確保するためには,まずもって調停調書や審判,執行受諾文言付公正証書の強制執行可能な形で作成してください。
そして,その後養育費の支払が滞ることがあれば,以上のような方法をとることで養育費の支払が確保することも考えられますので,一度検討してみてください。
申立ての方法が分からないということであれば,いつでもお気軽にご相談ください。 名古屋藤が丘事務所 弁護士横田秀俊
浜松事務所弁護士 横田 秀俊
- 7月
- 6
- Fri
宝くじ当選金の財産分与対象性については、過去にも当ブログで紹介いたしましたが(「これって財産分与になるの?宝くじ当選金の場合」)、近時、この点に関する裁判例が出ましたので、あらためて、ご紹介いたします。
財産分与とは、夫婦が婚姻中に夫婦の協力によって築いた財産を分配することを言いますが、宝くじの当選金は、財産分与の対象となるのでしょうか。たとえば、Aさんが、勤務して給与収入を得ており、その大半を家計にまわし(30万円程度)、残りを自身の小遣いにしていたとします(2、3万円程度)。Aさんがその小遣いの中から、毎月2000円を宝くじの購入にあてていたところ、ある日、2億円もの宝くじ当選金を得ることができました。Aさんの配偶者Bさんは、その後、Aさんと離婚した場合、宝くじ当選金の半分(1億円)を財産分与として請求することができるでしょうか。
ひとつの答えとして、東京高裁平成29年3月2日決定を参考にすると、宝くじ当選金も、財産分与の対象になると考えられます。つまり、Bさんは、Aさんに、宝くじ当選金の一部を請求することができるのです。この結論に対しては、Aさんは自らの(なけなしの)お小遣いの中から宝くじを購入していたので、宝くじ当選金はAさん固有の財産とすべきだ、との反論がありえます。しかし、宝くじ当選金のもとをたどると、Aさんの給与収入が原資となっており、Aさんの給与収入は、夫婦の協力によって築いた財産と考えられることから、宝くじ当選金も、夫婦共有の財産と考えられる可能性が高いのです。特に、宝くじ当選金の使い途が、夫婦が居住する住宅のローン返済にあてられていたり、夫婦の生活費にあてられていたりすると、一層、共有財産性を肯定します。
では、分与割合もAさん:Bさん=5:5になるのでしょうか。上記裁判例を参考にすると、Aさんが自らの小遣いの中から宝くじの購入を続けたことを重視し、Aさんが購入していなければ宝くじ当選金を取得することもなかったことから、財産形成の寄与についてAさんの方が大きいという判断がありえます。類似の事例である上記裁判例も、結論として、Aさん:Bさん=6:4の分与割合を認めました。
今回は、宝くじについての財産分与対象性、及び、その分与割合についての紹介でしたが、今後も類似の争点が出てくるものと思われます(投資の対象としての暗号通貨等)。資産形成について、本人の寄与度・才覚が問題となる場合は、分与割合が5:5にならない判断もあり得ます。お悩みの際には、一度、弊所にご相談下さればと思います。
名古屋丸の内本部事務所 弁護士柿本悠貴
名古屋丸の内本部事務所 弁護士 柿本 悠貴
- 5月
- 2
- Wed
離婚事件において、ご夫婦に未成年のお子さんがいる場合には、どちらが親権者となるか、養育費の支払い条件をどのようにするか、等とあわせて、お子さんとの離婚後の面会についてどのように定めるかが問題となるケースがしばしばあります。 離婚の成立前、成立後を問わず、子供らと同居していない親が、子供らとの面会を行うことを面会交流といいます。
面会交流については、一般論としては、実施されることが子どもの心理面の発達等に好影響を与える、とする論調が多く見られますが、離婚事件において面会交流の実施状況をみると、必ずしも面会交流の約束が定められているケースが多いとは言えないようです。また面会交流の約束が定められていても、現実にはこれが実施されないあるいは一時期実施されても継続的には行われないケースなども多いようで、全体としてみると面会交流の実施率はあまり高くないのが実情のようです。
こうした状況の一因には、面会交流について子どもの面倒を見ている親(監護親)が非監護親と子どもの面会交流に応じようとしない場合でも、これを強制することが難しかったという問題がありました。
この点については、最高裁判所が平成25年3月28日に、子どもと非監護親の面会交流を命じる審判があり、この審判の中で面会交流の日時又は頻度,各回の面会交流時間の長さ,子の引渡しの方法等が具体的に定められている場合には間接強制が出来る、という判断を下しました。要は、重要な部分について内容が一義的に明らかになっていれば罰金を払わせることで、事実上面会を強制できる、ということになります。 これ以降、家庭裁判所では審判を出すに当たって、間接強制の可能性も考慮して審判を下しているようであり、名古屋家庭裁判所で調停を担当していても、調停委員との間でそうした話が出ます。 もっとも、平成25年最判以降、全ての審判が強制執行可能な内容となっているわけではありません。というのも、この最判自体が、面会交流は子の利益を優先して、柔軟に対応可能な条項に基づいて両親の協力に基づいて実施されることが望ましいとしており、家庭裁判所も案件によっては、間接強制が可能となる形での審判を出していないようです。 面会交流を求めるに当たっては、相手方とのと間で任意の面会が期待できそうかどうか、それが困難な場合に間接強制を求めることが出来る条項を裁判所に定めさせることが出来るか等を含めて検討が必要であり、一度弁護士にご相談いただいてはいかがかと思います。 名古屋丸の内本部事務所 弁護士勝又敬介
- 2月
- 16
- Fri
内縁という言葉を聞いたことあるでしょうか?内縁とは法律による婚姻の届出がなく正式な夫婦とは認められないが,当事者の意識や生活実態において事実上夫婦同然の生活をする関のことで,事実婚とも言われています。
どのような関係があれば内縁と認められるかは難しい問題で,単に同居(同棲)しているだけではなく,家事を分担していたり,家計を管理したり,一緒に子供を育てていたり等,様々な事情から夫婦と同視できる実態があるかが判断されています。
では,内縁関係を解消したい場合,法律婚における離婚と比較して違いはあるのでしょうか。
内縁は法律上の婚姻ではありませんから,内縁を解消する場合に,夫婦の離婚に関する法律の規定をそのまま適用することはできませんが,他方で,出来る限り実態を重視して,法律上の結婚と同じように扱うべきと考えられています。
例えば,内縁を一方的に解消することはできず,離婚事由と同様の正当な理由が必要と考えられています。また,内縁の夫が,第三者の女性と性的関係を持った場合には,不貞行為として,内縁の妻は,内縁の夫や,第三者の女性に対し慰謝料を請求ができますし,内縁解消の際,内縁関係が成立して以降に内縁の夫婦で築いた財産については財産分与が認められています。
法的手続としても,離婚と同様,裁判所での調停等の手続もとることができますから,内縁の解消についても,法律上の婚姻における離婚の手続に近いといえるでしょう。内縁解消の問題は,離婚ほどメディアで取り上げられることもなく,インターネットなどを見てもあまり扱われていません。どのようにすればよいのかお一人で悩まれている方もいらっしゃるのではないでしょうか。
内縁を一方的に解消された,あるいは内縁の相手との関係に耐えられず内縁を解消したいといったお悩みにつきましては,是非弁護士にご相談頂ければと思います。