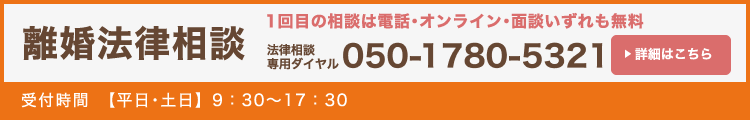離婚ブログ
過去の記事
- 11月
- 17
- Fri
浮気をしてしまった有責配偶者は、親権者にはなれないと誤解されている方がいらっしゃいますが、有責配偶者が親権者になれないということはありません。 親権者は、子どもにとって、どちらが親権者になる方が良いかという観点から決められるものであり、基本的に、浮気の問題は親権とは別問題と考えられます。 もっとも、浮気のために子育てがないがしろになっていたというような事情があれば、それは子との接し方の面でマイナス評価される可能性はあります。 いずれにしても、浮気については、親権の問題ではなく、慰謝料の問題として解決されるべき問題といえます。 しかしながら、浮気をしてしまったという負い目があると、ご自身で交渉する場合には、交渉が行いにくいという現実的な問題があります。 その場合は、交渉を弁護士に依頼することを検討する必要があります。 親権者を一度決めてしまうと、相手方に虐待や育児放棄などの特別な事情がないと親権者を変更することは難しいという現状がありますので、親権者を決める場合は、落ち着いて冷静に判断することが必要となります。 現在は、インターネットの発達により、様々な情報が飛び交っていますが、中には正しくない情報が混在していることも多いです。 思い込みによって、後悔しなくて済むように、一度弁護士に相談することをおすすめします。名古屋丸の内本部事務所 弁護士 水 野 憲 幸
- 9月
- 8
- Fri
離婚に際して子どもを引き取った親を監護権者,他方の親を非監護権者と呼んで,あるケースを紹介いたします。 子どもが会いたくないと言っているので面会交流を拒否することはできますか? こんな相談を受けることがあります。なかなか回答が難しい問題です。 面会交流とは,親の離婚によっても,子と非監護権者との間の親子関係は継続しており,子と非監護権者が交流することが,子の成長の過程で利益に資すると考えられているために実施されるものです。子どもが会いたくないにも関わらず,非監護権者に無理矢理会わせることで,子どもの心に傷を与えることになれば本末転倒となります。そのため,子どもが会いたくないということを理由に面会交流を拒否すべき場面があることは確かです。 他方,子どもにとって,親が離婚することで非監護権者とは離れて生活することになります。監護権者とのみ一緒に生活することで,知らず知らずのうちに,一緒に生活する監護権者に気を使って,「非監護権者に会いたくない」と言っているのかもしれません。
このように,子が非監護権者に会いたくないといっている場合,まずはその理由をしっかりと把握しなければなりません。監護権者に気を使っているだとか,非監護権者に会うのが何となく気まずい,と感じていることが理由であれば,監護権者としては非監護権者との面会交流を後押しし,面会交流を実施しやすい状況作りに協力すべき場合もあります。一度面会交流を実施することで,面会交流に対して子どもの抵抗がなくなるのであれば,やはり面会交流が子どもの成長の過程に資することになるからです。 監護権者と非監護権者とは離婚した関係ですので,監護権者にとって,子どもと非監護権者とが交流することに抵抗を感じることは珍しいものではありません。そのため,子どもが,「非監護権者に会いたくない。」と発言すれば,その言葉を鵜呑みにして面会交流を拒否してしまうことも珍しいものではないと思います。 しかし,面会交流は,子どもの成長の過程で利益に資するという観点から実施されるものですので,子どもが「会いたくない。」と言ったとしても,監護権者としては,子どもとしっかりと話し合って,子どもが本当に「会いたくない。」と思っているのかを見極めなければなりません。監護権者にとって,これは理屈では分かっても,実際に行動に移すとなると難しいものかもしれません。面会交流の実施について,悩むことがあれば,一度ご相談下さい。 春日井事務所 弁護士 森下 達
- 8月
- 4
- Fri
離婚後に、元配偶者と連絡を取り合うかどうかは、個々人の気持ちや状況次第のところもあります。円満な離婚であれば、離婚後でも連絡を取り合われる方もいるでしょうし、離婚原因によっては、もう連絡すら取り合いたくないと思われる方もいるでしょう。元配偶者と連絡を取り合うかどうかは、個々人で判断していただいてよいと思います。 しかし、元配偶者との間に子がいる場合には、全く連絡を取り合わないということは難しいかもしれません。養育費の支払や、子との面会交流等、子に関する連絡を取り合う必要性があるからです。場合によっては、子に関する連絡を取りたいのに、相手の住所や連絡先が分からなくなり、困ってしまう場合もあるのではないでしょうか。 そのような場合は、離婚時に、今後の連絡方法等を協議しておくことも大切です。
例えば、電話連絡で連絡を取り合うことや、電話連絡を避けたい場合にはメールやライン・手紙で連絡を取り合う等と連絡方法を協議しておきましょう。 また、住所や居所、連絡先や勤務先が変更になった場合に、お互いに速やかに通知するという協議をしておく場合もあります。 それらの協議内容については、離婚協議書や公正証書に書面として残しておくとよいでしょう。通知義務を怠った際にペナルティがあるわけではありませんが、書面に残しておけば、一応の心理的な圧力をかけることができます。 子にとっては、親の感情的な対立がストレスになることもありますので、子のために連絡を取り合う必要がある場合には、母親・父親としての冷静な対応を心掛けることが大切です。 小牧事務所 弁護士 奥村 典子
- 7月
- 25
- Tue
夫婦の一方から暴力を振るわれている場合に,どのように離婚手続を進めていけばよいでしょうか。このときに大切なことは,いち早く別居をするということです。暴力を振るわれている環境ではなかなか正常な判断をすることができません。また,交渉をするにしても相手方のほうが力関係が上であり,妥当な交渉をすることができません。ここで,特に女性の場合,仕事をしていない場合や,実家の援助を受けることができない場合もあり,別居後の生活環境を確保できない場合もあります。このときは,配偶者暴力相談支援センターや警察に保護を求め,緊急一時保護施設に避難することが可能です。また,相手方からの暴力をやめさせたい場合には,保護命令の申し立てを行うこともできます。これに違反して申立人に接近などした場合には,刑事罰を与えることが可能になるため,非常に強い抑止になります。ただし,「加害者からのさらなる身体に対する暴力により,その生命または身体に重大な危害を受ける恐れが大きいこと」などといった要件が必要となり,立証が困難な場合もあります。そのため,弁護士を活用していただき,DV対策を含めて離婚を進めていただくことも1つの手かと思います。DVで悩んでいる方は,是非一度当事務所の無料相談をご活用いただくことをお勧めします。 小牧事務所 弁護士 遠藤 悠介
- 5月
- 22
- Mon
離婚に関わる問題を解決する際には,多くの書類を準備する必要があります。離婚問題が持ち上がったのを機に別居を始めるようなケースでは,「書類を自宅を置いてきてしまった!」というケースも少なくありません。
共働きの夫婦の一方が自宅を出て別居するケースについて,別居の前に準備しておくと良い書類をご紹介します。
1 まずは,別居期間中の婚姻費用(生活費)を計算するために,夫婦の収入を把握することが必要です。
勤務先から前年の12月に発行された源泉徴収票の写しを準備しましょう。源泉徴収票に書かれている「支払金額」欄の金額をもとに,別居期間中の婚姻費用を計算することになります。
「支払金額」が各々600万円と300万円で,子供の年齢が0歳~14歳の夫婦では,年収300万円の方が子供を連れて別居する場合には,自宅に残る方が月額6~8万円の婚姻費用を分担する必要があります。
共働きの夫婦の場合には,夫婦両方の「支払金額」をもとに婚姻費用を計算することが必要になりますし,離婚後の養育費を算定する際にも「支払金額」を参照する必要があります。
別居前に婚姻費用の支払いについての話し合いをしていないケースでは,生活費を確保するため,なるべく早い時期に婚姻費用の請求を行う必要があります。
その際には,源泉徴収票が必要になりますので,同居期間中に手元で保管するようにしておきましょう。
すでに勤務先を退職していて源泉帳票の再発行を受けられないような場合には,住所地の市役所・区役所で前年分の所得証明書を入手しておきましょう。
なお,家庭裁判所に婚姻費用分担調停を申し立てる際には,直近の給与明細3ヵ月分の提出を求められることがあります。別居前に手元で保管するようにしておきましょう。
2 次に,同居期間中に夫婦で築き上げた財産(これを「夫婦共有財産」といいます。)を把握することが必要になります。①預貯金,②自動車,③持ち家,④負債について説明します。
①預貯金
預貯金は,原則として別居時点の残高が,財産分与のもとになるプラスの財産としてカウントされます。通帳記帳を行って,別居日の直近の残高を確認しておきましょう。
ご自身名義の通帳に関しては,直近の通帳だけでなく,ご結婚から別居開始日までの取引履歴が記載された全ての通帳を手元で保管するようにしましょう。財産分与の際には,別居時の残高を夫婦共有財産としてカウントすることが多いですが,結婚の時点で相当な残高があれば,その分が夫婦共有財産から除かれる可能性があります(この方がより多くの財産分与を受けることができます。)
また,日頃から相手方名義の通帳を管理している場合には,銀行名・支店名・預金種別・口座番号の控えをとっておきましょう。いったん別居を始めてしまうと,相手方がどこの銀行・支店に口座を持っているのか探索することは難しくなります。別居前に必要な情報の控えをとって,いざというときに残高の開示を求められるようにしておくことが重要です。
控えをとる際には,相手方名義の口座からご自身名義の携帯電話料金・生命保険料・損害保険料が毎月幾ら引き落とされているかもチェックしておきましょう。いずれはご自身で支払いをしていかなければならない費用ですし,婚姻費用の支払いを受ける際に差し引かれる可能性もあるので,あらかじめ金額を確認しておく必要があります。
②自動車
自動車は,時価が財産分与のもとになるプラスの財産としてカウントされます。
時価は,車種・年式・型式・走行距離・車検残期間を,中古車価格情報誌やウェブサイトの中古車検索を利用することにより算出します。
車検証に載っている情報をもとに算出することになりますので,車検証の写しを1式準備しておきましょう。
③持ち家
持ち家等の不動産も,時価が財産分与のもとになるプラスの財産としてカウントされます。
まずは,住宅購入時の書類一式の写しを準備しておくことが有効です。不動産の登記簿謄本,住宅購入時の契約書,住宅ローンの支払予定表が一緒になっていることが多いので,それぞれ写しをとって手元で保管しておきましょう。
不動産に関しては,価格を評価する際,「固定資産税評価額」が参考資料になりますので,市区町村の窓口で土地・建物の固定資産評価証明書を1通取得しておくと良いです。
持ち家の購入時には,いずれか一方のご両親から金銭的援助を受けて購入することも多いかと思います。このような場合には,持ち家の購入金額に対するご両親の援助額の割合に相当する金額を特有財産としてカウントすることがあります。
具体的には,4000万円の持ち家を,貴方の両親から1000万円の援助を受けて購入し,別居時の時価が3200万円になっている場合には,3200万円×1000万円÷4000万円=800万円は財産分与の対象から除外され,2400万円が財産分与の対象になります。
両親からの援助を受けて持ち家を購入した場合には,援助額が幾らだったのかも確認しておきましょう。
④負債
自動車や持ち家については,ローンで購入することが少なくありません。ローンは,財産分与のもとになるマイナスの財産としてカウントされます。夫婦が婚姻期間中に築き上げたプラスの財産とマイナスの財産を合計して,マイナスが出れば,原則として財産分与は行われません。
住宅ローン,自動車ローンのいずれについても,支払予定表を取りそろえておきましょう。
これらは,共働きの夫婦の一方が自宅を出て別居するケースをもとにした一例に過ぎません。実際にはご夫婦の状況に応じたきめ細かな調査が必要になります。
当事務所では,「必要書類一覧表」を公開しております。
法律相談にお越しになる前にこちらからダウンロードし,可能な範囲で必要事項を記入していただくと,正確なアドバイスをさせていただくことが可能になります。
https://rikon.aichisogo.or.jp/flow/pdf/sodanForm1.pdf
名古屋丸の内本部事務所 弁護士 横 井 優 太