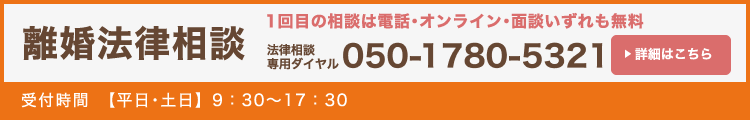離婚ブログ
過去の記事
- 4月
- 10
- Mon
離婚をするときは,財産分与について話し合います。財産分与とは,夫婦で貯めた財産を,基本的には2分の1に分ける手続きです。 財産分与の対象としては,不動産や預貯金等があります。その他,生命保険についても財産分与の対象となることがありますので,見落としてしまったということがないように注意して下さい。
では,生命保険はどのようなときに財産分与の対象となるのでしょうか。
財産分与は財産的価値のあるものを分ける手続きですので,当該生命保険に財産的価値がなければなりません。そして,生命保険については,解約返戻金が出る場合,財産的価値のあるものと考えます。
婚姻生活が長くなれば,生命保険の解約返戻金が100万円を超えることも珍しくありませんので,財産分与の際は注意して下さい。
財産分与の方法としては,生命保険を解約して返戻金を分けることもあれば,生命保険に加入し続けたまま,保険名義人が相手方に金銭を分与して調整することもあります。
その他,婚姻前から保険料を支払っていた場合,生命保険が子供名義になっていた場合,学資保険の場合等,保険に関しては様々な問題が生じます。
具体的なお話しを伺いますので,是非一度ご相談に頂ければと思います。
名古屋藤が丘事務所弁護士 長江 昂紀
- 3月
- 21
- Tue
今回は,「すでに離婚をしたが,離婚のときに特に条件を定めなかった」という場合についてお話したいと思います。 離婚において,「子どもの親権をどうするか」は必ず決めなくてはならない事項です。日本の法律では離婚のときに親権者を定めることになっており,離婚届にも親権者の記載欄があります。
これに対して,財産分与,養育費,慰謝料といった財産上の問題については,離婚時に決める必要がありません。
もちろん弁護士が離婚手続きに介在するときは財産上の問題についても検討するのですが,夫婦だけで協議離婚を行った方のなかには,財産上の問題については特に考えずに離婚だけした,という方も多くいらっしゃるのではないでしょうか。 何も定めずに離婚をしたあとでも,財産上の問題をあらためて決めることは可能です。
時効の問題はありますが,あらためて相手方と協議することはもちろん,裁判上の手続きを利用することも可能です。
「子どもがいないので養育費は請求できない」,「夫婦間に特にめぼしい財産もないので財産分与も請求する必要がない」,という方も,年金分割に関しては定めておくべきではないでしょうか。
年金分割とは,婚姻期間中の厚生年金,共済年金の保険料納付を分割して,夫婦双方の年金額を変更しようとする制度です。例えば,妻が専業主婦だった場合,離婚後の妻の年金額が少なくなり,生活に困窮してしまうことが予想されます。
そこで,年金分割により,婚姻期間中の夫婦双方の保険料納付額自体を変更する必要があるのです。離婚から2年以内であれば,離婚後であっても年金分割を行うことができます。
年金分割には合意分割と3号分割という二つの制度があります。合意分割は夫婦で合意して保険料納付額の分割割合を定める手続きです。ただし基本的には分割割合は0.5,つまり等分に分けるということになるかと思います。
3号分割は「平成20年4月以降分」かつ「請求者が3号被保険者(会社員や公務員の配偶者の扶養に入っていた人)」の場合に合意なしに強制的に分割割合を0.5として年金分割を行う手続きです。
3号分割であれば一人で手続きが出来ますが,平成20年4月以前から結婚していた方や共働きだった方の年金分割には合意分割部分が出てくることになります。
離婚後に思い立って合意分割を行う場合,原則として元夫婦双方が二人で年金事務所に行く必要があります。愛知県内の年金事務所は,名古屋市東区,名古屋市南区,名古屋市西区,名古屋市北区,名古屋市中区,名古屋市中村区,名古屋市昭和区,名古屋市熱田区のほか,名古屋市外にも8カ所あります。
二人で一緒に行くのは抵抗があるという方であれば,弁護士等,代理人を立てることも可能です。分割割合について合意できない,相手方が年金事務所まで来てくれないという場合は,裁判所に調停を申し立てることになるだろうと思います。
苦労して離婚したあと,さらにお金のことで相手と交渉するのは嫌だな,と感じる方は多くいらっしゃると思います。しかし,離婚後の人生を考えたときに,お金のことについて決めておくことは大切なことです。時効の問題もあるので,いつまでも後回しにできるわけでもありません。
愛知県近隣にお住まいの方で,こういったお悩みをお持ちの方は,是非一度当事務所の無料相談にいらっしゃることをお勧めします。 高蔵寺事務所 弁護士 服部 文哉
- 3月
- 3
- Fri
名古屋市内でも最高気温が14℃となるなど,日中はだんだんと寒さも和らぎ,ひと足早い春の訪れを感じる季節となりました。 さて,本日は,男女問題をテーマに,事例を交えてお話させていただきたいと思います。
弊事務所にも日々,様々なご相談が寄せられますが,男女問題の中で比較的ご相談が多いのが,「不倫(不貞行為)の慰謝料」についてです。 最近では,週刊誌が世間を騒がせたり,テレビドラマで題材として取り上げられたりするなど,日常生活においても,不倫や不貞という文字を目にする機会があるのではないでしょうか。
また,現在,夫(妻)に不貞行為をされていて相手に慰謝料を請求したい,あるいは,不貞相手の夫(妻)から慰謝料を請求されていてどう対処したらいいのか分からないなど,一人でお悩みの方もいらっしゃるかと思います。
請求する側もされる側も,慰謝料はいったいいくらが適正な金額なのかは,統一的な算定基準がなく,とても難しい問題です。
Aさんは,スポーツジムで知り合ったBさんと不貞をしてしまい,このことがBさんの夫であるCさんに発覚してしまいました。Aさんは,話し合いのために直接Cさんと面談をしたところ,その場で慰謝料300万円の支払いに合意するよう強く求められました。Aさんは,Cさんに対する罪悪感や恐怖心から,その場で承諾してしまいそうになりましたが,何とか結論は持ち帰ることとし,すぐに弁護士に相談しました。
その後,弁護士がAさんの代理人としてCさんと交渉し,本件での不貞期間,不貞行為の態様,どちらが主導的役割を果たしたか,婚姻期間,婚姻関係破綻の有無など,具体的な事情を考慮した結果,最終的に100万円で解決することになりました。
不貞相手の配偶者との面談については,心理的に多大な躊躇を覚えることが自然ですから,不貞を行った人の立場としては,高額な慰謝料額を提示されたとしても,減額を求めたり,支払可能性について冷静に検討したりすることは難しく,相手の言うとおりに条件を承諾してしまう傾向にあります。
しかし,上記の例でいえば,Aさんがいったん300万円の支払いに合意し,念書や合意書を作成してしまえば,後からその効力を争い,無効とすることは困難です(なお,不貞慰謝料1000万円の支払合意について,合意の効力が無効とされた裁判例(東京地判平成20年6月17日)もありますが,1000万円というのは不貞慰謝料として相当に高額ですので,特殊な例でしょう。)。
Aさんの場合は,その場でCさんの提案どおりの条件で合意することなく,すぐに弁護士に相談にこられたので,事案に則した適正な金額をCさんにお支払いする方法で解決することができました。
慰謝料の請求を考えておられる方はもちろんですが,慰謝料を請求されてお困りの方も,一度,弁護士に相談することを検討されてはいかがでしょうか。
名古屋丸の内本部事務所 弁護士 中 内 良 枝
- 1月
- 10
- Tue
離婚に関する法律問題は多様であり,それぞれに夫婦につきどれが問題になるかも変わってきます。 あえて大きく区別をするのであれば
①そもそも離婚することができるか,離婚しなければならないのかという問題と
②離婚するとしてどのような条件を定めるのか,離婚しないとしてどのように生活環境を整えていくのか
という問題に分けられます。
①の問題として典型的なものが「有責配偶者の離婚請求」です。婚姻関係の破綻の原因を一方的に作り出した場合は,相手方の同意がない限り離婚を実現することが難しくなります。
有責配偶者で離婚調停を申立、離婚成立した事案
私は,離婚事件を受任する際に,紛争の長期化を避け,一回的な解決を実現するため,原則として①の問題と②の問題を同時に交渉する方が望ましいと考えます。
もっとも,各相談者様のご意向によっては一概にそうとはいえません。上述した有責配偶者の離婚請求の場合,条件面で全く折り合いがつかない場合でも離婚自体に争いがないのであれば,条件面をさておいてでも離婚の実現を図るべきだといえるでしょう。
離婚に限らず法律問題の難しいところは,各相談者様ごとによって抱えている事情が全く異なるため,何が最善の方法であるかを個別に検討する必要がある点です。お気軽にご相談いただき,相談者様にとって最善となる方法を一緒に発見・検討させていただきたいと思います。
名古屋丸の内本部事務所 弁護士 米 山 健 太
名古屋丸の内本部事務所弁護士 米山 健太
- 10月
- 7
- Fri
夫婦の間に未成年の子がいる場合には、離婚時に、子の親権者を妻か夫のどちらにするか決めなければなりません。
離婚後も、子が父及び母の双方と良い関係を築き、心身共に健やかに成長していけるためには、どのような面会交流が望ましいかをよく考え、条件を定めておくことが大切です。1 面会交流の条件を定める方法
1.協議(夫婦での話合い)、2.調停があり、調停でも意見が合わない場合には、3.審判に移行し、裁判官が条件を決定することになります。
2 審判における判断要素
では、面会交流はどのような観点で定められるのでしょうか。裁判所は、「子の福祉に合致するか」、つまり、子にとって何が望ましいかという観点で判断し、その判断においては、以下のような要素が考慮されます。
(a)子の事情
子の意思(15歳以上であれば子の意見を聞かなければなりません。)、子の年齢(子の年齢が高くなるほど面会による動揺などの影響のおそれが少なくなります。)、面会交流による子への影響が出ないか等が考慮されます。 (b)親権者の事情
面会交流をすることによる子の養育監護への影響が出ないか等が考慮されます。 (c)親権を得ない親の事情
面接交渉をさせない方が良い事情の有無(たとえば暴力や暴言)等が考慮されます。3 面会交流の内容
面会交流の条件は、定型的なものがあるわけではなく、個々のケースに応じて柔軟に定めることが可能です。
月に何度会うのか、夏休みや冬休みなどの長期休暇には宿泊を伴うのか、電話やメールは自由にできるのか、お小遣いは渡して良いのか、子の写真送付などの間接的な交流を認めるのか等につき、子の福祉を第一に考えながら定めていきます。
4 定めた面会交流が実現されない場合
調停または審判で定められた面会交流が実現されない場合には、親権を得なかった親は、再度調停を申し立てる、履行勧告(履行するよう裁判所に注意してもらう)、間接強制(約束を破る度に罰金何円支払うという方法)の方法をとることが考えられます。
なお、履行勧告や間接強制の方法によることができるのは、面会交流の条件を調停または審判で定めた場合に限られます。 子が父母双方の愛情を感じ、安心して信頼関係を築いていけるような面会交流を実現できるよう、きちんと条件を定めておくことが大切です。
面会交流は、離婚の前後を問わず話し合うことができますので、お気軽に弊所までご相談下さい。