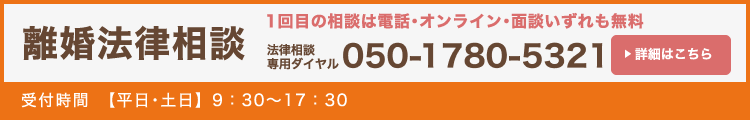離婚ブログ
過去の記事
- 2月
- 8
- Fri
1 はじめに
離婚前に,別居にふみきる場合,夫婦の荷物を完全に分離せず,取り急ぎ,必要な荷物のみを搬出することが多いかと思います。
大半の夫婦は,夫婦関係が悪化した中で十分な協議を経ることなく,別居生活を開始するわけですので,別居後に,荷物の受け渡しを要してしまうことがあり得ます。
そこで,今回は,別居後に自宅への立ち入りが生じた場合の対応方法についてお話させていただこうと思います。
2 自宅への無断立ち入りの可否
別居後,自宅を離れた方は,自分の家なのだから自由に出入りしたいと考えるかもしれません。
しかし,他方配偶者が自宅を単独で管理するに至った場合,自分の家であっても,住居に無断で立ち入ると,住居侵入罪(刑法第130条前段)に該当する可能性があります。 ご自身の荷物であっても,他方配偶者に無断で持ち出せば,窃盗罪(刑法第235条)に該当する可能性もあります。ただし,夫婦間の窃盗は刑法上,処罰を受けないことになっています(第244条1項)。
実際に,警察が介入することは少ないかもしれませんが,民事上の損害賠償責任を追及されたり,感情対立を悪化させたりしかねませんので,自宅を管理する他方配偶者の許可を得ない立ち入りは控えるべきといえます。
3 自宅への立ち入り拒否の可否
他方で,別居後に自宅に残った方は,他方配偶者の来訪を拒絶したいと考えるかもしれません。
しかし,自宅は,共同生活中の夫婦の生活拠点であったはずですので,自宅内には相手方配偶者の財産が散在するはずです。
そのため,自宅への立ち入りを一律に拒否できるわけではありません。少なくとも,自宅内の他方配偶者の荷物の持出については,協力をはかる必要があるといえます。
4 持ち出し可能な荷物
自宅を離れた方の特有財産は持ち出し可能です。
自宅を単独管理する配偶者の許可があれば,夫婦共有財産の持ち出しも可能です。
特有財産とは,夫婦の一方が婚姻前から有する財産や,婚姻中に自己の名義で得た財産(例えば,相続により所有するに至った財産等)のことです。
夫婦共有財産とは,婚姻生活中,夫婦の協力によって築いた財産(例えば,夫婦の給与で購入した家財等)のことです。
5 立ち入り等の交渉
事前に,他方配偶者と,立ち入りの日時等を調整しておくことをお勧めします。夫婦共有財産と特有財産は判然としないことがありますので,持ち出す物についても,きちんと確認しておくべきです。
当事者間での協議が困難な場合には,代理人弁護士をつけて,弁護士を介して交渉することをお勧めします。
6 おわりに
別居後に自宅への立ち入りや荷物の持ち出しで揉めると,離婚協議が停滞したり,感情対立が激化し,交渉が難航したりする危険があります。
別居後を見据えた別居前の対策については,横井優太弁護士による2017年5月22日投稿のブログ「別居を考えたときに準備する書類」もご参考にしてください。
別居中の自宅の立ち入りや荷物の持ち出しにあたっては,夫婦共有財産該当性や,立ち入り拒否の合理性等,高度に専門的な判断を迫られるといえます。
別居中のトラブルでお困りの方は,是非,弊所にお気軽にご相談ください。
名古屋新瑞橋事務所 弁護士田村祐希子
東京自由が丘事務所弁護士 田村 祐希子
- 1月
- 30
- Wed
離婚に伴って養育費の具体的な金額について取決めを行うケースは多いと思いますが,そのような取決めを裁判所で行っていても,後に事情の変化があったときにはその増減を求めることができる場合があります。
民法880条には扶養義務関係について変更を生じたときは以前の取決めを変更できる旨規定していて,例えば減額の典型例としては当事者の再婚が挙げられます。
ただし,このように減額自体は認めていますが,義務者(支払っている側の人)が勝手に減額をしてよいものではなく,当人同士で協議をするか,それが難しい場合には家庭裁判所に対して養育費の減額調停を申し立てなければなりません。勝手に養育費を減額してしまうと,過去に取決めをした際の裁判所の調書や公正証書に基づいて強制執行をされてしまう可能性があるので注意を要します。
上記に関連してよく受ける相談としては,権利者(養育費を貰う側。多くの場合元妻)が再婚した場合に養育費を減額してもよいのかというものがあります。
この場合,単に元妻が再婚したというだけであれば,親子関係には影響がないので,基本的に養育費の支払いに影響はありません。
しかし,再婚だけでなく,その再婚相手が子どもと養子縁組までした場合には,養親である再婚相手が第一次的に扶養義務を負うことになりますので,再婚相手に経済力があれば養育費が減額できる場合もあります。
今回は,権利者が再婚した場合に減額できるかどうかにしぼってご説明しましたが,具体的なケースごとに金額の変更が認められることは当然あり得ることです。
離婚後に事情の変化が生じることは長い人生においては当然のことですので,養育費の金額の変更が必要と考えられた場合は一度当事務所にご相談ください。
- 12月
- 7
- Fri
1.はじめに
この記事をお読みになっている方の中には,配偶者からのDVでお悩みの方もいらっしゃるかもしれません。
DV対策については,当ブログの過去記事(DV対策 )でもご紹介させていただいておりますが,今回は,「暴力をふるった配偶者から別居先を追跡されない方法」についてお話をさせていただければと思います。
2.こんなお悩みはありませんか
配偶者からのDVが原因で,身体の危険を感じた際に,どうしても別居先を隠しながら別居せざるをえない場合もあるかと思います。
また,特に,就学中のお子様がいらっしゃった場合には,別居先の学校に転校するために,住民票を別居先の住所に移動させる必要 も出てきます。
しかしながら,配偶者は,もう一方の配偶者の住民票を取得することが可能です。そこで,配偶者の地位を用いて,住民票を取り付けると,別居先の住所が明らかになってしまう可能性があります。
そんな場合に必要になるのが「住民基本台帳事務におけるDV等支援措置」です。
3.支援措置の内容,方法
この支援措置を講じれば,住民票の写しの交付や,住民基本台帳の一部の写しの閲覧,戸籍の附票など,住所が分かる資料の閲覧を制限することができます。
これができれば,住民票から追跡を受けることはできなくなります。
支援措置を受けるためには,警察や,配偶者暴力相談支援センターに相談して,支援措置を受けることが相当であるという意見をもらう必要があります。
その上で,住民票のある市区町村や戸籍の附票のある市区町村等に,この意見を記載した書類を提出することで,支援措置を講じてもらうことができます。
4.今後のご相談について
今回は,役所で行っている支援措置の制度についてご紹介させていただきましたが,暴言・暴力・DV等の根本的な解決ではありません。
暴言・暴力・DV等でお悩みの方は,是非弊所までご相談ください。
大阪心斎橋事務所弁護士 岩田 雅男
- 10月
- 22
- Mon
未成熟子がいる場合の離婚に関しては,養育費が問題となることが多くあります。養育費についてしっかり取り決めをせずに離婚してしまうと後々紛争になりかねませんので,養育費については,離婚時に適切に取り決めておく必要があります。 養育費とは,そもそも,未成熟子が社会人として独立生活ができるまでに必要とされる費用のことをいい,未成年者の範囲とは必ずしも一致しないとされています。 したがって,子が社会に出て稼働している場合,例えば高校を卒業して就職した場合などには,その子は未成熟子とはいえず,養育費は請求できないものとされています。 一般的には,養育費の終期を未成熟子が成人に達したときとする扱いが多いですが,父母の学歴などの家庭環境,資力により個別に定めることができます。 裁判例(大阪高裁平成29年12月15日決定)においても,父が医師であり,母が薬剤師である夫婦が,離婚の際に,子が大学(医学部を含む)を卒業するまで養育費を支払うほか,私立大学医学部に進学する場合,子が直接父に希望を伝え,不足分については別途協議する旨協議条項に定めていたところ,子が私立大学医学部に進学したものの父が追加費用を支払わなかったため,子が父に対して追加費用の請求をした事例において,協議条項を合意するに至った経緯,父の属性,子の進路等に関する父の意向等を総合考慮すれば,父は,離婚当時,子が私立大学医学部への進学を希望すればその希望に沿いたいとし,その場合,養育費のみでは学費等を賄えない事態が生じることを想定し,子からの申し出により一定の追加費用の負担をする意向を有していたと認めるのが相当である,として子の父に対する追加費用の請求を認めました。 このように,離婚時にあらかじめ父母の学歴などの家庭環境や資力等を踏まえ,想定される費用がある場合には,そのような費用も考慮して養育費の取り決めを行うことが重要となります。 養育費は,未成熟子の衣食住のための費用や健康保持のための医療費など生存に不可欠な費用のほか,未成熟子がその家庭の生活レベルに相応した自立した社会人として成長するために必要な費用も含む重要なものです。 そのため,離婚を考えられる際には,養育費について,弁護士等の専門家にご相談の上,適切な取り決めを行うことをお勧めいたします。離婚の際に,条件の取り決めに不安がある方は,ぜひ当事務所にご相談いただければと思います。 名古屋丸の内本部事務所 弁護士黒岩将史
名古屋丸の内本部事務所弁護士 黒岩 将史
- 9月
- 14
- Fri
愛知総合法律事務所の弁護士加藤純介です。さて,今回のブログのテーマは,「離婚と戸籍の関係」です。最近ではあまり聞かなくなった印象もありますが,「戸籍が汚れる」という表現が,昔からあります。
この,「戸籍が汚れる」とはどういう意味なのでしょうか。
離婚の回数を示す「バツ○」の「バツ」とは一体何のことなのでしょうか。かつて,今のように戸籍が電子化されていない時代,戸籍は全て手書きで作成されていました。そして,離婚した場合には,戸籍から抜けることになりますが,戸籍から抜けたことを示すために,バツ印を付けていました。これが,離婚を示す「バツ」の由来です。単にバツを付けるだけでは離婚した方は戸籍上消滅してしまうので,
①もといた戸籍に戻る
②新たな戸籍を作る
といったことが必要です。
もといた戸籍に戻る場合には,もともとの記載部分については既にバツ印が付いてしまっているので,バツ印を消すのではなく,新たに名前を記載する必要がありました。
これが,「戸籍が汚れる」と表現されたのでしょう。ただ,最近は,電子化の時代です。
戸籍についても電子化されており,現在では,戸籍にバツ印が付けられることはありません。単に「除籍」と記載されるにとどまります。また,かつて第三者が戸籍を自由に見ることができた時代もありますが,現在では,第三者が自由に戸籍を閲覧することはできません。さて,離婚を考えた時に,離婚すべきかしないべきか,非常に悩むことがほとんどだと思います。家族のこと,子どものこと,夫婦で築いてきた財産のこと,たくさんのことを悩まれると思います。この時に,「戸籍が汚れる」ことを気にして,離婚をためらわれる方もいるのではないかと思います。
そして,上のような説明を聞くことで,漠然とした「戸籍が汚れる」という不安が無くなる方もいらっしゃるのではないかと思います。離婚は非常に多くの問題が絡むため,分からないことが多すぎて,どこから考えたらいいのか分からない,何を悩んだらいいのか分からない,といった状況に陥ることも珍しくありません。
愛知総合法律事務所の弁護士が,ご相談者様おひとりおひとりの事情を丁寧に伺い,ご疑問点にお答え致します。こんなこと弁護士に聞いて良いのかな,と思われるようなことでも,一度弁護士に相談してみることで,前に進むことができるかもしれません。
離婚について分からないこと,困っていることがある方は,お気軽に一度ご相談ください。 名古屋丸の内本部事務所 弁護士加藤純介